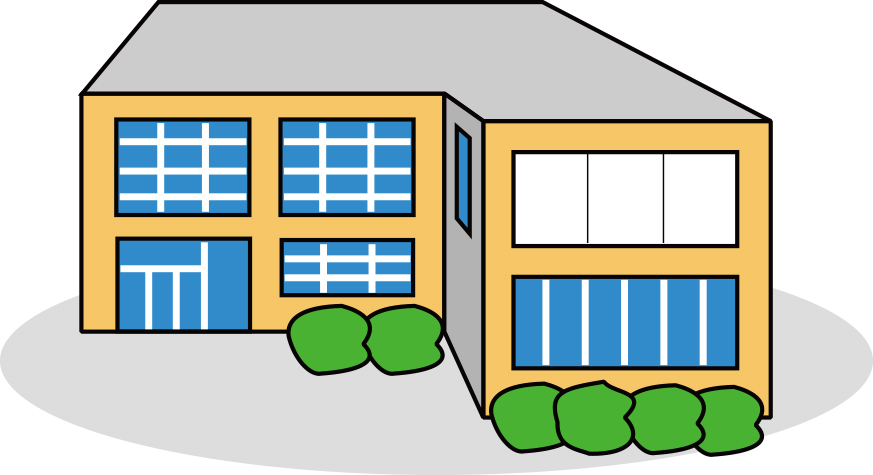加賀藩の塩硝作りは、いつごろから始まったか、二つの説があります。
- 元亀元年(1570)、石山の本願寺は織田信長に対抗するため、火薬を五箇山で作るよう塩硝技術者を五箇山へ派遣した。
- 利賀の西勝寺は、加賀の人、洲崎恒念を大阪・堺へ派遣して製造法を習わせた。(『真宗五箇山史』より)
五箇山産の塩硝は、質、量とも日本一でした。百科事典に「加賀より産するもの最上品とし、筑前(福岡県)はこれにつぐ」。森重流の砲術書にも「加賀のものが第一級品、その硝石の山元は五箇山という深山」とあり。五箇山の塩硝は文字どおり全国一と記されています。
五箇山は豪雪地帯で、冬期は完全に隔絶され、農民たちは、それまで炭焼き、養蚕、和紙作りなどで、細々と生活していました。この地は塩硝製造に好適で、豊富な燃料、清冽で低温の豊かな水に恵まれ、江戸時代の書「毛吹草」に「越中、飛騨、安芸、美作」と記され、加賀藩はこの書でもトップにランク付けされています。